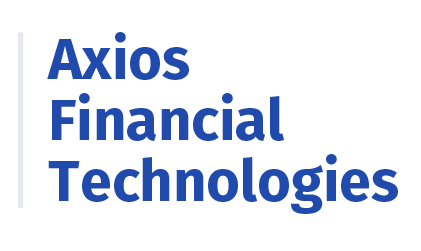企業価値向上を目指す経営者にとって、「成長戦略」「財務戦略」「株主還元戦略」の三要素は、いずれも無視できない重要な柱である。だが、これらは常に調和するとは限らない。成長を優先すれば財務に歪みが生じ、株主還元を強化すれば将来投資の余力が削がれる──この三者の間に生じる緊張関係を、本稿では「企業価値向上のトリレンマ」と呼ぶ。
このトリレンマは、企業ごとに異なる形で現れる。以下では、三つの二項対立を通じて、それらの力学を読み解いていく。
1. 成長戦略と財務戦略のトレードオフ
成長を志向する企業は、当然ながら積極的な投資を行う。研究開発、新規事業への進出、M&A──いずれも多額の資金を要する。だが、その資金を調達する手段によっては、財務の安定性を損なうリスクが生じる。
たとえば、大規模なM&Aに伴う多額の借り入れは、資本構成を不安定にしかねない。仮に成長が想定どおりに進まなかった場合、ROICは資本コスト(WACC)を下回り、企業価値の毀損に直結する。つまり、投資は資本コストを上回る期待リターンが見込まれる場合にのみ正当化されるのであり、これは財務戦略との慎重な整合が求められる所以である。
2. 成長戦略と株主還元戦略のトレードオフ
資金には限りがある。成長投資に資金を振り向ければ、株主への配当や自社株買いに充てる余力は自然と減る。とりわけ成熟企業にとって、安定した株主還元は投資家との信頼関係を支える基盤であるため、その水準を下げることは短期的に株価下落を招く可能性がある。
一方で、配当や自社株買いに過度に依存すれば、投資資金が乏しくなり、将来の成長機会を自ら閉ざすことになりかねない。したがって、資本配分の優先順位は、その企業がいまどの成長ステージにあるのか──黎明期か、成長期か、成熟期か──を見極めたうえで判断されるべきである。
実際に米国企業を対象に行った実証研究では、配当や自社株買いを優先しすぎた結果、将来の成長に向けた設備投資やR&Dが不足し、企業の競争力が低下したという研究結果も報告されている*。
3. 財務戦略と株主還元戦略のトレードオフ
財務の健全性を維持しようとすれば、手元資金や自己資本比率を厚く保つ必要がある。だが、それは往々にして「使われない資金」を企業内に滞留させ、資本効率(ROEやROIC)の低下につながる。
一方で、積極的に株主還元を進めるために、資本を自己株買いや配当に振り向ければ、今度は自己資本が薄くなり、財務レバレッジが高まる。財務健全性の指標であるD/Eレシオやインタレスト・カバレッジ・レシオが低下すれば、格付けや調達コストにも影響する。まさに、企業は「安全性」と「効率性」という相反する要請の間で綱渡りをしている。
トリレンマを乗り越えるために
このように、成長、財務、株主還元はそれぞれが企業価値に影響を与える要素でありながら、完全に両立させることは困難である。だからこそ、経営者には明確な優先順位付けと、トレードオフの理解が求められる。
時に、三者のバランスを取ることが最適解となる場合もあるが、局面によっては、あえて一要素に舵を切り、他の二つを一時的に犠牲にする戦略が有効となることもある。たとえば、大規模な成長投資を行うフェーズでは、あえて株主還元を抑制し、財務負担を一時的に許容する覚悟が必要かもしれない。
重要なのは、こうした意思決定が「企業価値の最大化」という原則の下に行われているかどうかである。そしてその判断には、ROICとWACCの差分に基づく残余利益モデルや、資本配分の妥当性を示す各種指標を用いた冷静な分析が不可欠である。
終わりに
本稿で提唱している「企業価値向上のトリレンマ」は、経営の現場におけるリアルな葛藤を映し出す概念である。成長投資、財務規律、株主還元──これらの間で揺れ動く意思決定こそが、企業経営の本質であるとも言える。
読者には、自社や投資先企業の戦略が、このトリレンマのどこに軸足を置いているのかを見極める視点を持っていただきたい。本稿がその一助となれば幸いである。
* EM Turco, 2018, “Are Stock Buybacks Crowding Out Real Investment?”