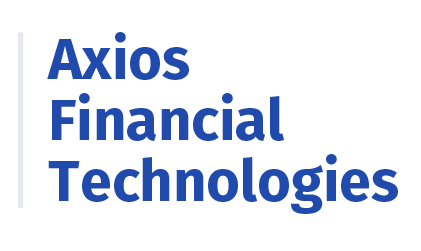“資本コストや株価を意識した経営”の重要性が叫ばれて久しい。コーポレートガバナンス改革の進展に伴い、上場企業の経営者にはこれまで以上に企業価値を意識した経営が求められている。その一環として、金融庁は2019年3月期以降、有価証券報告書において株主総利回り(TSR: Total Shareholder Return)の開示を義務付けた。しかしながら、TSRは単なる開示項目として捉えられており、十分に経営に活かされているとは言い難い。
実際、多くの企業のIRサイトではTSRの数値が掲載されているものの、その具体的な意味や経営との関係性について十分な説明がなされていない。経営陣の報酬がTSRに連動していると明示している企業もあるが、実際にどのような経営判断が企業価値向上に結びついたのかが説明されているケースは少ない。むしろ、EVA(Economic Value Added)の提唱者であるBennett Stewart氏は、TSRに基づくインセンティブ設計は、経営者の努力とは無関係に結果が決まる可能性があり、「宝くじ」のようなものだと指摘している。
さらに、TSRをTOPIXと比較して示す企業も多いが、この比較が経営上の意思決定に示唆を与えるかは疑問である。第一に、TOPIXは個別企業の特性を反映しない。株価は金利、為替、景気循環など多様なマクロ要因の影響を受けるが、それらの影響は企業ごとに異なる。第二に、TOPIXとの比較は、競争戦略や資本配分といった具体的な経営判断に直結しない。TOPIXをベンチマークとすることは、投資家にとっては有意義かもしれないが、経営者にとっては必ずしも意味のある比較とはいえない。
このように、TSRは十分に活用されていないが、実は企業価値向上を目指す経営者にとって極めて有用な指標である。TSRは株式の値上がり益(キャピタルゲイン)と配当などの還元(インカムゲイン)の合計として定義される。このうちキャピタルゲインは、株価の変化を「売上高の成長率」「利益率の変化」「PER(株価収益率)の変化」の三要素に分解して理解することができる。
例えば、株価が100円から360円に上昇した場合、この間のキャピタルゲインは260%(=360/100-1)となる。売上高が100円から120円、純利益率が10%から20%、PERが10倍から15倍に変化したと仮定すれば、120/100×20%/10%×15/10-1=260%となる。この分解は、株価の変化を経営がコントロール可能な要素(売上・利益率)と、投資家の評価(PER)に切り分けて捉えることを可能にする。
このような分解を通じて、「売上もマルチプルも伸びているのに株価が伸び悩む」のであれば利益率が課題であり、「売上・利益率ともに好調なのに株価が低迷する」のであれば、IR活動が不十分で投資家の評価が追いついていない可能性があるといった、打ち手のヒントが浮かび上がる(なお、最近の研究2によれば、マルチプルの変化もファンダメンタルで説明可能であり、結局は「ファンダメンタルの改善が企業価値向上の最重要課題である」という結論に至ることが多い)。
実際に、ある上場企業の支援において、株主総利回りの分解を活用し、「ファンダメンタルは競合他社より優れているが、コングロマリットによる制約から、この事業は最適なオーナーではない」と提案した結果、事業売却が迅速に検討され、株主総利回り分析の効果を実感した。
TSRを分解し、競合比較と組み合わせて活用することで、単なる数値の開示から一歩踏み込み、企業価値向上のための実践的な経営ツールとして機能させることができる。資本コストや市場の期待を意識した経営を進める上で、TSR分解は強力なレンズとなり得る。単なる報告義務としてではなく、経営者自らの武器として、TSRを積極的に活用する時代が来ているのではないだろうか。
1. Bennet Stewart, (2014) “What determines TSR”. Journal of Applied Corporate Finance
2. Paul Geertsema, Helen Liu (2022) “Relative Valuation with Machine Learning”, Journal of Accounting Research